最初の1時間でやること3つ
- 医師による死亡確認
- 葬儀社に連絡
- 家族への連絡
PDFこちら
「もしものとき」にすぐやること(時系列チェックリスト)
【1】ご臨終直後(まず最初に行うこと)

- 医師に連絡する
・自宅で亡くなった場合 → かかりつけ医または救急に連絡し、「死亡確認」をしてもらう。
・病院で亡くなった場合 → 病院で死亡診断書が発行される。 - ご家族・近親者に連絡する
・すぐ来てほしい家族・兄弟などを中心に。
・連絡は電話が確実。LINEなどは補助的に。 - 葬儀社に連絡する(24時間対応)
・遺体搬送のため、まず1社に決めて依頼。
・すでに決めている葬儀社があれば、事前登録の電話番号に連絡。
・未定の場合は、病院から紹介を受けず、自分で選ぶ方が安心(後で費用トラブル防止)
【2】ご安置~打ち合わせ前にやること

- 安置場所を決める
・自宅または葬儀社の安置施設。
・マンションなどで安置が難しい場合は、葬儀社施設が多い。 - 宗教・宗派を確認する
・仏教・神道・キリスト教・無宗教などを確認。
・お寺・菩提寺がある場合は、早めに連絡を入れる。 - 葬儀の形を家族で相談する
・家族葬・一日葬・直葬・一般葬など。
・故人の意向がある場合は尊重する。
【3】葬儀社との打ち合わせ時に準備するもの

- 故人の情報(氏名・生年月日・住所など)
- 喪主を決める
- 日程(お寺や火葬場の都合と調整)
- 予算の目安(例:30万〜200万円)
- 写真(遺影用・スマホ写真でも可)
- 衣類(ご納棺用の服があれば)
【4】葬儀までに行う手続き・連絡
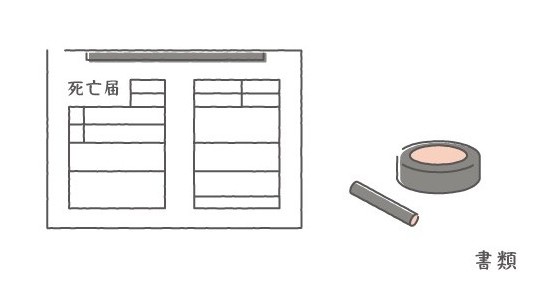
- 死亡届を提出する
・医師の「死亡診断書」を持って市区町村役場へ(葬儀社が代行することも多い)。
・提出後、「火葬許可証」が発行される。 - 弔問の対応・香典辞退の方針
・弔問を受ける範囲を家族で決めておく。
・家族葬なら「故人の遺志により、近親者のみで行います」と伝える。 - お通夜・告別式の案内
・親族・親しい友人・勤務先などへ案内。
・日程と場所が確定してから一斉に伝える。
・参列者の人数を確認する。
・お料理(通夜ぶる舞い、精進落とし料理)をされる場合の数を確認する。
【5】葬儀後(落ち着いたら)
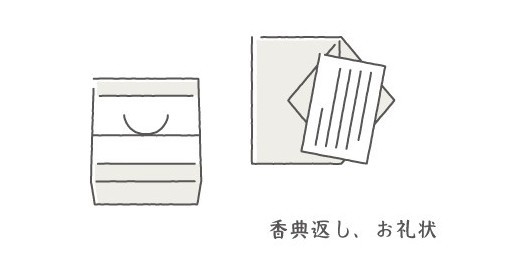
- 香典返し・お礼の挨拶
- 役所・年金・保険などの手続き
- 四十九日・納骨の準備