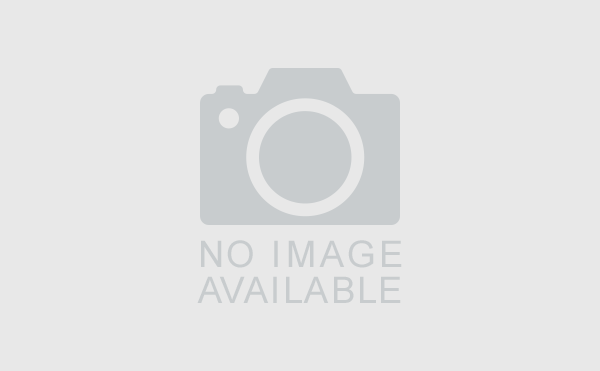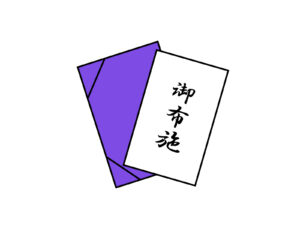豆知識⑦友引とは?
みなさん!こんにちは!
先週末から雨が続きますねー(*‘ω‘ *)
ジメジメだったり寒く感じる日々であります(*’ω’*)
さてお話は、変わりますがみなさんもお聞きしたことがあるかと存じますが
実際のお葬式では、火葬場の日程やお寺様(お坊様)などとお話で”友引”で、
日程を変えることがございます(´・ω・`)
そちらについてお話をしたいと思います(`・ω・´)ゞ
友引とは・・・
「友引(ともびき)」は、日本の六曜(ろくよう)のひとつです。六曜は、暦の中で日の吉凶(縁起の良し悪し)を表す指標で、主に冠婚葬祭などの行事で参考にされます。
友引の意味と由来:
- **「友を引く」**という字の通り、「その日の運命が友にも及ぶ」と解釈されます。
- 一般に、「勝負事は引き分け」、「大きな凶はないが、友に災いが及ぶかもしれない日」とされます。
主な使われ方:
- お葬式を避ける日とされています。
- 「友を引く」→「死者が友を道連れにする」と解釈され、火葬や葬儀を避ける習慣があります。
- 結婚式など慶事には比較的良い日とされることもあります。
- 凶日ではないため、お祝いごとは問題ないという見方もあります。
時間帯による吉凶(例):
- 友引の日は、時間帯によっても吉凶が変わるとされ、午前と夕方は吉、中昼は凶とする説もあります。
六曜はあくまで民間の慣習で、宗教的な根拠はありませんが、今でもカレンダーや冠婚葬祭の場面では意識されることが多いです。
「六曜(ろくよう)」とは、暦に記される6種類の吉凶を示す日柄(ひがら)のことで、日本や中国の暦で使われてきた伝統的な暦注(れきちゅう)のひとつです。主に冠婚葬祭や行事の際に、「縁起の良し悪し」を判断する目安とされています。
六曜の種類と意味:
- 先勝(せんしょう/さきがち)
午前は吉、午後は凶。急ぐことに向く日とされる。
→ 「早くやれば吉」といわれる。 - 友引(ともびき)
基本的に吉。ただし葬式は凶とされる。
→ 「友を引く」=死者が友を道連れにするという俗信。 - 先負(せんぷ/さきまけ)
午前は凶、午後は吉。争い事は避けたほうが良い日。
→ 「急用は避け、静かに過ごすと良い」とされる。 - 仏滅(ぶつめつ)
最も凶の日とされ、祝い事は避けられる傾向にある。
→ 「すべてが滅する日」という解釈がある。 - 大安(たいあん)
最も吉の日。結婚式や開業などの慶事に最適とされる。
→ 「大いに安し」=何をするにも良い日。 - 赤口(しゃっこう/しゃっく)
凶日。ただし「午(うま)の刻」(午前11時~午後1時)のみ吉。
→ 火や刃物に関係することに注意が必要とされる。
六曜の由来:
- 中国の「小六壬(しょうろくじん)」という占いが起源とされ、日本では江戸時代後期から広まりました。
- 明治時代に一度は禁止されましたが、その後もカレンダーなどに記されるようになり、今も民間で広く使われています。
注意点:
- 六曜には宗教的な裏付けはなく、科学的な根拠もありません。
- あくまで「縁起を担ぐ」習慣であり、参考程度にする人も多いです。
葬儀を友引の日に避ける理由は、以下のような俗信・迷信に基づいています:
【理由】
「友引」=「友を引く」
→ 死者があの世へ旅立つ際に「友(親しい人)を道連れにして引っ張る(=死に巻き込む)」とされるためです。
【具体的な影響】
- 遺族や参列者の間で「縁起が悪い」とされ、心理的な抵抗感があります。
- そのため、多くの人が葬儀を友引の日以外にずらす傾向があります。
- 火葬場も友引は休業になる地域が多く、実務的にも葬儀ができない場合があります。
【例外・補足】
- 宗教的には特に根拠がないため、仏教・神道などの教義とは無関係です。
- 友引でもやむを得ず葬儀を行う場合、**「友引人形」(ともびきにんぎょう)**を棺に入れて「身代わり」にするという風習もあります(地域による)。
つまり、「友引に葬式をしない」のは宗教ではなく、日本独自の風習・忌み言葉への配慮です。
友引を避けて葬儀を行う際の日程調整には、以下のような実務的・心情的な配慮ポイントがあります:
葬儀の日程調整の具体的なコツ
1. 六曜カレンダーを事前に確認する
- インターネットや市販のカレンダーには六曜付きのものが多いです。
- 通夜・葬儀・告別式のすべてを友引以外の日に設定するのが一般的。
- 特に葬儀(告別式)の日を友引にしないことが重視されます。
2. 火葬場の稼働日を確認する(友引は休みのことが多い)
- 多くの火葬場が友引は定休日になっているため、物理的に実施できません。
- 葬儀社が空き状況を把握しているので、まず葬儀社に相談するのが効率的です。
3. 友引を挟む場合、「1日空けて」調整するのが通例
- 例:亡くなったのが月曜で、火曜が友引 → 水曜に通夜、木曜に葬儀。
- 通夜を友引にすることは比較的許容されますが、葬儀当日が友引なのは避ける傾向が強いです。
4. 「友引人形」で対応する地域もある
- 地域や家族の考え方によっては、「友引人形」を棺に入れることで友引日でも葬儀を行うケースがあります。
- これは「死者が友を引かず、人形を身代わりにする」という考えに基づくものです。
5. ご遺族・参列者の都合も加味する
- 日程変更によって遠方からの参列が難しくなることもあるため、なるべく早く関係者に共有しましょう。
- 葬儀社は経験豊富なので、日程調整から火葬場予約、友引の回避策まで一括で相談可能です。
📝 まとめ
| 調整項目 | ポイント |
|---|---|
| 六曜確認 | カレンダーやネットで事前確認 |
| 火葬場 | 友引休業の有無を葬儀社と確認 |
| 日取り | 通夜はOKでも葬儀は友引NGが一般的 |
| 代替策 | 友引人形を使う方法もあり(地域差) |
※関東圏では、あまり友引人形を使用してお葬儀をすることは、ほとんどございません。
地方出身の方がその地の風習習慣にならい行うのがある場合がございますがほとんど執り行うことが少ないです。
友引人形とは?
**友引人形(ともびきにんぎょう)**とは、**友引の日に葬儀を行う際に、死者が親しい人を道連れにしないようにするための「身代わりの人形」**です。主に日本の一部地域で使われる、民間信仰に基づいた風習です。
🔸 目的・意味
- 「友引=友を引く」という俗信から、「死者が誰かをあの世に連れて行かないように」と願って、人形を棺に入れます。
- 人形が「友人や家族の代わり」に旅立ってくれるという意味が込められています。
🔸 特徴
- 多くは紙製または木製の小さな人形。
- 顔が描かれていたり、簡素な衣装がついていることもあります。
- 一般には簡素な作りで、「ひとがた(人形)」のようなものが多いです。
- 地域によっては「死に装束」と一緒に入れられることも。
🔸 地域性・注意点
- 関西・中部・東北などの一部地域で見られる風習で、全国的には一般的とはいえません。
- 宗教的な裏付けはなく、完全に風習・迷信の範囲です。
- 仏教・神道では、特にこの人形を使う決まりなどはありません。
🧭 豆知識
「友引でもどうしても葬儀をしたい」場合の心の安心材料として用いられることがあります。
一部の葬儀社では、友引人形を用意してくれることもあります。
友引人形の風習が残っている地域は、日本全国では少数派ですが、主に中部地方・関西地方・東北地方の一部で見られます。以下に代表的な地域とその特徴をまとめます。
🗾 友引人形を使うことがある主な地域
1. 中部地方
- 愛知県、岐阜県、静岡県など
- 特に名古屋市周辺では、友引人形を「必須」とする家もあります。
- 葬儀社や仏具店で「友引人形付きの葬儀プラン」がある場合も。
2. 関西地方
- 京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県の一部
- 地域差があり、使うかどうかは家の考えや宗派によって異なる。
- 紙で作られた簡素な「人形(ひとがた)」を入れる風習がある。
3. 東北地方
- 宮城県や山形県などで一部風習が残る。
- 友引を避けられない場合、心の安心として使われることがある。
🚫 あまり行われない or 知られていない地域
- 関東地方、北海道、九州地方などでは、この風習自体がほとんど知られていないことが多いです。
- 「友引に葬儀をしない」ことは広く意識されていますが、「人形を入れる」風習は一般的ではありません。
友引人形


このようなお人形さんを使用します。
関東では、あまり馴染みがほとんどないですがしっかり個人様に寄り添ってご一緒にお旅立ちをしていただきます。その他に以下のような例があります。
🧸 友引人形の写真例
1. 布製の友引人形
白い着物を着たシンプルな布製の人形で、故人の身代わりとして棺に納められます。
2. 手作りの軍手人形
家族が軍手を使って作成した手作りの友引人形。故人のひ孫が顔を描き、メッセージを添えるなど、心温まるエピソードもあります。
3. 伏見人形の友引人形
京都の伝統工芸品である伏見人形の一種。五人の子供が並んだ形をしており、友引の日に棺に入れる風習があります。
4. ぬいぐるみを代用した友引人形
故人が生前大切にしていたぬいぐるみを友引人形の代わりに棺に納めることもあります。特に決まった形がないため、故人や遺族の思いを反映させた選択が可能です。
友引人形は地域や家庭の風習によって異なりますが、共通して故人の旅立ちを見送る際の心の支えとなる存在です。
一般的な友引人形には「男性用」「女性用」といった性別の区別はありません。
✅ 理由と背景
- 友引人形はあくまで「身代わりの存在」であり、性別に意味を持たせる必要がないとされています。
- 多くの友引人形は「男女の区別のない無性の姿」か、**簡素な人型(ひとがた)**です。
- 和紙・布・紙粘土・伏見人形など、素材や形に地域性はありますが、性別で分ける文化はほとんど見られません。
🧸 例外的に見られるケース(まれ)
- 故人の性別に合わせて人形の装いを変える家庭もごく一部にあります(例:髪の長い女性型、着物の色柄)。
- ただしこれは「宗教的慣習」ではなく、遺族の気持ちや演出の一環であることがほとんどです。
💡 まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一般的な扱い | 性別なし。男女区別しないのが通例。 |
| 宗教的意味 | なし。地域の風習・民間信仰の一環。 |
| 例外 | 希望に応じて装飾に工夫を加えることも可能。 |
今回は、友引についてお話をさせていただきました。
また、知りたいことなどございましたらインスタグラムやXなどでもDM
下さい。お応えいたしております(`・ω・´)ゞ
このへんで!またまた!
#友引#お休み#東村山#お葬式#お葬儀#家族葬#火葬場#都内
#小人数#多摩地区#埼玉県#お花#費用#一日葬#お通夜#告別式#直葬#小規模
#火葬式#事前相談#小さな#お葬式#よりそう#明朗会計#安心#信用#地域密着