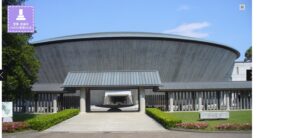豆知識⑯供物・盛物について
こんにちは!どーもかんべでございます(`・ω・´)ゞ
連日ジメジメの梅雨になってしまい湿度といきなり晴れて暑くなったりと大大大変な日々でありますね
とうとうエアコンを動かしました(*‘ω‘ *)
あの感覚がとても幸せです。

さてさてお話は、変わり御供物と盛物のお話お話
「葬儀供物(そうぎくもつ)」と「盛物(もりもの)」は、葬儀の際に故人への供養や弔意を示すために供える品物ですが、それぞれに意味や形式があります。
【葬儀供物とは】
**供物(くもつ)**は、故人への供養として祭壇やお墓に供える品の総称です。葬儀や法要などで用いられます。
主な供物の種類:
- 果物かご:リンゴ・バナナ・オレンジなどの季節の果物を詰めたかご。
- 菓子折り:饅頭、羊羹、クッキーなどの詰め合わせ。
- 乾物類:海苔・昆布・椎茸など日持ちする食材。
- 缶詰セット:缶詰食品やジュースなど。
※地域や宗派によって形式が異なる場合があります。
【盛物とは】
**盛物(もりもの)**は、供物の一種で、果物や野菜などを美しく盛り付けたものを指します。神道の儀式や一部の仏式葬儀でも用いられます。
盛物の特徴:
- 見た目を重視:美しく、バランスよく配置される。
- 素材は自然のもの:果物(りんご・みかんなど)や野菜(大根・にんじんなど)を使う。
- 意味合い:自然の恵みを神仏や故人に捧げる「感謝」と「清らかさ」の象徴。
違いのまとめ:
| 項目 | 葬儀供物 | 盛物 |
|---|---|---|
| 目的 | 故人への供養・弔意 | 神仏・故人への感謝の表現 |
| 内容 | 食品、果物、乾物など | 果物や野菜の盛り合わせ |
| 見た目 | 包装・箱詰めが多い | 美しく盛り付けられる |
| 宗教対応 | 仏教、神道、無宗教 | 神道や仏教(地域による) |
東京都・埼玉県の葬儀における「供物」と「盛物」の習慣には、地域性・宗派・式場の運営方針による違いがいくつか見られます。以下にその概要を整理します。
🏙️ 東京都・埼玉県における供物・盛物の習慣
1. 供物の一般的習慣
✅ 主な形式
- 果物籠(くだものかご)、菓子折り、乾物セット、缶詰セットなどが主流。
- 最近は**「盛り籠(もりかご)」**と呼ばれる、包装された食品詰合せが一般的。
- 地域性よりも「式場のルール」と「家族の希望」によって形式が決まることが多い。
✅ 誰が贈るか
- 遠方の親族、知人、取引先などが「供花・供物セット」として手配。
- 親族や施主側は「辞退」することも増えている(香典や花に集中するため)。
✅ 供物に関する傾向
- 会葬者が減少傾向 → 大量の供物を受け取らない方針の家族も多い。
- 一日葬・家族葬の普及 → 式場が小さいため、供物を省略するケースもある。
- 供物は現物よりも「供物料(現金)」で済ませるケースも。
2. 盛物の地域的な扱い
✅ 盛物とは(再確認)
- 神道でよく見られる「果物・野菜を美しく盛った供物」。
- 関東(特に埼玉)では、農業地域の伝統として「お清め」「自然の恵みへの感謝」を込めて使われることがある。
✅ 盛物が用いられるケース
- 神道葬(埼玉の一部地域)
- 地域密着型の寺院葬・自宅葬で、昔ながらの風習が残っているところ。
- ただし、都市部では簡略化される傾向。
✅ 盛物の今の立ち位置
- 東京23区内ではあまり見かけない(スペース・形式の問題)。
- 埼玉(特に農村部・地域密着型の式場)では今も使われる場合がある。
- 祭壇の両脇に飾る形で、地域のJA(農協)や地元商店が用意することもある。
📌 式場によるルールの違い
| 式場タイプ | 供物可否 | 盛物可否 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 民間斎場(例:ティア・さがみ典礼) | ◯ | △ | 盛物は応相談、供物は事前申込制 |
| 公営斎場(町屋斎場、戸田葬祭場など) | ◯ | △ | 場所によって制限あり |
| 自宅葬・寺院葬 | ◯ | ◯ | 地域色や宗派の影響を受けやすい |
| 家族葬ホール | ◯(制限あり) | × or △ | 省スペースのため制限されること多い |
📝 遺族側の選択傾向(東京都・埼玉県)
- 「供物はお断り」や「供物は現金で」が増加中。
- 供物を飾るスペースの有無で可否を判断。
- 最近は「供花のみ受け付け」「供物は1~2基に限定」という案内も増えている。
🔎 まとめ
| 地域 | 供物 | 盛物 | 傾向 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 一般的 | 少ない | 式場によって制限あり、簡素化傾向 |
| 埼玉県 | 一般的~地域色 | 地域によっては残る | 農村部や神道葬では今も見られる |
宗派によって**供物(くもつ)や盛物(もりもの)**の扱いや意味合い、供え方には違いがあります。以下に主な宗派別の特徴をわかりやすくまとめます。
🛕 仏教宗派ごとの供物・盛物の特徴
| 宗派 | 供物の特徴 | 盛物の扱い | 備考 |
|---|---|---|---|
| 浄土真宗 | ✕あまり供物を重視しない(故人の成仏は阿弥陀仏の本願によるため) | ✕不要・供える習慣ほぼなし | 「供物辞退」が多く見られる宗派 |
| 浄土宗 | ◯果物や菓子、乾物などを供える | △あっても簡素 | 他力本願だが、供養の実践も重視 |
| 曹洞宗(禅宗) | ◯季節の果物、野菜、白米を丁寧に供える | △使われることも | 盛物も禅的に「質素で清らか」なものが良しとされる |
| 臨済宗(禅宗) | ◯曹洞宗とほぼ同様 | △簡素な盛物可 | 規律に基づく供養を重視 |
| 日蓮宗 | ◯果物・菓子など多め | ◯行事によっては使われる | 仏壇への日常的な供物習慣も根強い |
| 天台宗・真言宗 | ◯供物が多く豪華な場合も | ◯伝統的な盛物あり | 密教系は法要が荘厳で供物にもこだわりあり |
🏯 神道の場合(盛物が最も象徴的)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 供物 | 果物・野菜・米・塩・水・酒などの「自然の恵み」 |
| 盛物 | 神前に丁寧に盛り付けられた供物が中心 |
| 特徴 | 「神饌(しんせん)」と呼ばれる儀礼用の供物が決められている。祭壇(神饌台)に整然と並べる |
| 例 | りんご・みかん・ほうれん草・白菜などを高盛にして、紅白の紙などで飾る |
💡 無宗教葬・自由葬の場合
- 形式にとらわれず、供物を出さないケースも多い。
- 飾るとしても「故人の好きだった物(お酒や趣味の品)」を簡単に置く。
- 盛物のような形式は避け、ナチュラルでシンプルな装飾が主流。
🔎 宗派別供物・盛物の違いまとめ(簡易表)
| 宗派 | 供物の有無 | 盛物の有無 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 浄土真宗 | △(形式的) | ✕ | 供物を供える意味を重視しない |
| 浄土宗 | ◯ | △ | 果物・菓子類が多い |
| 禅宗(曹洞・臨済) | ◯ | △ | 簡素で質素な供養が基本 |
| 日蓮宗 | ◯ | ◯ | 派手な供物や装飾も見られる |
| 天台・真言 | ◯ | ◯ | 豪華で儀礼的 |
| 神道 | ◯(神饌) | ◯(中心的) | 盛物は神への敬意の象徴 |
| 無宗教 | △ | △ | 故人や家族の希望優先 |
📌 実務的なポイント(東京都・埼玉県の葬儀現場では)
- 宗派よりも「家族の意向」と「式場のルール」が優先されるケースが多い。
- 式場スタッフや葬儀社が「宗派に合う供物を選定・制限」してくれる。
- 一日葬や家族葬では「供物辞退」「供花のみ受付」とする案内が多くなっている。
宗派ごとに「供物(くだもの籠・盛籠・菓子折りなど)」を贈る際、**芳名板(木札・名札)の表書き(上段の言葉)**には適切な表現があります。これは宗教的な意味や作法に基づくもので、正しく書くことで失礼なく弔意を示すことができます。
🧾 芳名板(供物札)の構成
通常、以下のような形式になります:
コピーする編集する【上段(表書き)】:供物の目的を示す言葉(宗派によって異なる)
【下段(差出人名)】:個人名または会社名
🛕 宗派別|供物の芳名板・表書きの例
| 宗派 | 表書き(上段) | 備考 |
|---|---|---|
| 浄土宗 | 御供(おそなえ) | 一般的に無難。 |
| 浄土真宗 | 御仏前(ごぶつぜん) | ※「供物を供える」という思想に消極的なので、供物自体を辞退するケースも多い。御供も可。 |
| 曹洞宗 | 御供 | 果物・乾物などの供物が用いられる。 |
| 臨済宗 | 御供 | 同上。御仏前でも可。 |
| 日蓮宗 | 御供 / 御仏前 | どちらも一般的に使われる。 |
| 真言宗 | 御供 / 御仏前 | 密教でも供物の意味を重視。 |
| 天台宗 | 御供 / 御仏前 | 同上。 |
| 神道 | 御玉串料 / 御神前 / 奉献 | ※供物の札では「奉献」が一般的。玉串料は金銭の場合。 |
| キリスト教 | 献花 / 供花 | 供物を贈ること自体が少ないが、贈る場合は「献花」「御花料」など。 |
| 無宗教 | 御供 / 献花 | 故人や遺族の意向に合わせるのが基本。 |
✅ 無難に使える表書き(迷ったら)
- 仏教全般:「御供」でほぼ問題ありません(最も汎用的)
- 神道:「奉献」または「御神前」
- 宗派不明・遺族の意向優先:「御供」または事前確認
🎯 実務的な注意点(東京・埼玉エリア)
- 式場スタッフや葬儀社が芳名板を代筆・印刷することがほとんど。
- 差出人名の表記は、「◯◯株式会社 代表取締役 ◯◯◯◯」など正式名で。
- 宗派が不明な場合、施主(喪主)または葬儀社に確認するのが安心です。
📌 例文(仏教:一般的な表記)
コピーする編集する御供
株式会社あおばフラワー
代表取締役 ○○太郎
神道やキリスト教における**供物(くもつ)や盛物(もりもの)**には、それぞれ独自の意味と形式があります。仏教とは異なる思想に基づいており、供える品物や儀礼も特徴的です。
⛩️ 神道の供物・盛物の特徴
✅ 基本的な考え方
- 神道では、故人は**祖霊(みたま)**となり、神に近い存在として祀られます。
- 神に捧げる供物は「神饌(しんせん)」と呼ばれ、**清らかさ(清浄)**が最も重視されます。
✅ 供物の内容
神饌や供物の中身は以下が典型です:
| 種類 | 内容例 |
|---|---|
| 米(生米または炊いた白米) | 神の主食とされる |
| 酒(神酒) | 清酒 |
| 水 | 「おみず」として神前に供える |
| 塩 | 清浄の象徴 |
| 野菜・果物 | 大根・人参・みかん・りんごなど季節のもの |
| 魚 | 尾頭付き(例:鯛)※地域による |
✅ 盛物の形式
- 白木の三方(さんぽう)や折敷に盛り付け。
- 紅白の紙をあしらったり、**榊(さかき)**と一緒に供える。
- 美しく、高く盛るのが基本(=**「高盛」**という形式)。
✅ 芳名札(供物札)の表書き
- 「奉献」「御神前」「御玉串料」など。
- 「御仏前」や「御供」は使用しません(仏教語)。
✝️ キリスト教の供物・盛物の特徴
✅ 基本的な考え方
- キリスト教では、供物という形式的な供え物の習慣は基本的にありません。
- 故人は神の元に召されるとされ、個人崇拝や物理的な供養は行わないためです。
✅ 葬儀時の供え物(例外的な対応)
| 内容 | 備考 |
|---|---|
| 献花(白い花) | 一般的で重要。白百合や白いカーネーションなど。 |
| 故人の好きだった品 | 家族葬などで遺影の近くに飾られることもある。 |
| 果物・菓子類 | ごく一部で飾るケースもある(形式よりも心を重視) |
※ただし、形式よりも「祈り・心・思い出」を重視するため、供物・盛物は控えめか、省略されることが多いです。
✅ 芳名札(供物札)の表書き
- 「献花」「御花料」が適切。
- 「御供」「御仏前」などの仏教語は絶対に避ける。
✨ 比較まとめ表
| 項目 | 神道 | キリスト教 |
|---|---|---|
| 供物の考え方 | 神への捧げ物(神饌) | 故人ではなく神への祈りが中心 |
| 盛物の有無 | ◯ 高盛の果物・野菜など | ✕ 基本的に存在しない |
| 主な供物 | 米、酒、水、塩、果物、野菜、魚など | 白い花(献花)、遺品的なもの |
| 形式 | 清浄・整然・神聖な配置 | シンプル・控えめ |
| 芳名板表書き | 奉献、御神前、御玉串料 | 献花、御花料 |
🔍 実務のポイント(東京都・埼玉県の葬儀で)
- 神道葬儀は**埼玉の一部地域(農村部や伝統の強い家庭)**で見られます。供物・盛物は丁寧に扱われる傾向。
- キリスト教葬儀では「供物は省略」「供花のみ」の案内が一般的。白い花のみで統一されることが多いです。
- 宗教の形式に合わない供物や札の表書きは「非常に失礼」にあたるので、事前確認が大切です。
神道およびキリスト教の葬儀で見られる供物・盛物の「形式例(飾り方や実際の供え物)」をビジュアル的にイメージできるようにご紹介します。葬儀会場での実務にもとづいた例を簡単に整理しました。
⛩ 神道の供物・盛物|形式例
① 神饌(しんせん)の盛物セット(基本例)
| 内容 | 形式と意味 |
|---|---|
| 白米 | 三方(白木の台)に山型に盛る。 |
| 塩・水 | 塩は小皿に山型、水は白磁の器に。 |
| 酒 | 白い瓶子(へいし)に神酒を入れて供える。 |
| 果物 | りんご・みかんなど季節の果物を3〜5個で高盛。 |
| 野菜 | 大根・人参・ほうれん草など。彩りも考慮。 |
| 飾り | 白い半紙・奉書紙、紅白の水引を添えることも。 |
※配置は「左右対称」、清浄で整った印象が重視されます。
※会場では神職または葬儀社スタッフが設置します。
📸 イメージ例(言葉による描写)
コピーする編集する・白木の祭壇中央に榊が飾られ、
・その前に「三方(台)」が並び、
・一つ一つの台に、山盛りの果物や野菜、小皿に塩・水・酒が供えられる。
・周囲には白い布または和紙で覆われ、非常に清浄感のある印象。
✝ キリスト教の供物形式|例
キリスト教では供物は行わないのが原則ですが、遺族や会葬者の希望によって以下のような形式が見られます。
① 献花形式(最も一般的)
| 内容 | 形式と意味 |
|---|---|
| 白百合・カーネーション | 故人の霊に祈りを込めて捧げる。祭壇または棺の前に供える。 |
| バスケット型花籠 | 白や淡色の花で統一し、会社名などを芳名板に記載。 |
→ 芳名板の表書きは「献花」「御花料」が一般的。
② 故人の好物などを自由に配置(自由葬型)
| 内容 | 形式 |
|---|---|
| 故人の写真まわりに好物(コーヒー、パンなど) | 非公式・自由形式。祈りの象徴として。 |
| メッセージカード | 花と一緒に添えることがある。 |
📸 比較形式イメージ
| 項目 | 神道 | キリスト教 |
|---|---|---|
| 盛物 | ◎(正式儀式の一部) | ✕(基本なし) |
| 供物の種類 | 米、酒、塩、水、果物、野菜、魚など | 白花・好物(自由形式) |
| 盛り方の形式 | 白木の台(三方)に高盛・神前に整列 | 花籠・献花を整然と配置 |
| 表書き札 | 奉献 / 御神前 / 御玉串料 | 献花 / 御花料 |
🎁 実際の取り扱い例(参考)
- **神道葬(埼玉の一部エリア)**では「JAが提供する果物の高盛セット(5,000円〜)」が使われることがあります。
- **キリスト教葬(東京23区内)**では「白花のみ可」「供物は一切不可」の式場も多く、宗派(カトリック・プロテスタント)によっても異なる。
今日はこの辺で!またまた!
#盛物#供物#関東#東村山#お葬式#お葬儀#家族葬#火葬場#都内
#小人数#多摩地区#埼玉県#お花#費用#一日葬#お通夜#告別式#直葬#小規模
#火葬式#事前相談#小さな#お葬式#よりそう#明朗会計#安心#信用#地域密着
#神道#キリスト教#仏式#無宗教#お香典